地方に暮らす高齢者にとって、バスは「命綱」ともいえる大切な交通手段です。
しかし近年、乗客の減少や運転手不足などの影響で、各地でバスの減便・廃止が相次いでいます。
「週に一度の病院通いも難しくなった」「買い物ができない」「人と会う機会が減って気持ちが沈む」──そんな声が増えています。

■ 現実に起きている「交通弱者」問題
人口減少地域では、1日に数本しかバスが走らないというケースも少なくありません。
朝と夕方に1本ずつ、日中は“空白時間”になる地域も。
結果として、車を手放した高齢者が「外出できない」状態に陥る例が増えています。
また、病院やスーパーが郊外に集中している地域では、
「買い物難民」「通院難民」と呼ばれる人々も増加。
単に不便なだけでなく、健康悪化や孤立、認知症の進行といった深刻な影響にもつながっています。

■ 家族にも重くのしかかる「移動の問題」
高齢の親がバスを利用できなくなると、家族が送り迎えを担うケースも増えます。
「毎週の通院送迎で仕事を抜けられない」「買い物や役所の用事も全部車で…」といった声は多く、
家族の生活負担も大きくなっています。
都市部では想像しにくいかもしれませんが、
「免許を返納した親が1人で生活するには、車がない=生活できない」という現実が、地方では確実に広がっています。
■ 解決策①:自治体の「乗合タクシー」「デマンド交通」の活用
近年、多くの自治体で導入が進むのが「デマンド交通」と呼ばれる仕組みです。
電話や予約アプリで希望時間を伝えると、地域の小型車両が迎えに来てくれるもので、
料金はバス並みに抑えられている場合がほとんどです。
高齢者がスマートフォンを使えない場合でも、
電話予約で利用できる自治体も増えています。
市町村の広報誌やホームページを確認してみましょう。

■ 解決策②:家族で「移動支援」を仕組み化する
家族だけで送迎を抱え込むのは大変です。
地域によっては、シルバー人材センターの「送迎ボランティア」や有償運送制度も活用できます。
また、親が使いやすいスマートフォンの地図アプリや乗換案内を一緒に設定しておくと、
「安心して出かけられる自信」につながります。

■ 解決策③:シニアカーや電動アシスト自転車の導入
短距離の移動には、電動シニアカーや電動アシスト自転車も選択肢です。
最近は操作も簡単で、免許不要。
バス停やスーパーまでの“ちょい乗り”に最適です。
「転倒が心配」という声もありますが、
屋根付き・低速型・安定設計のモデルも多く、一人暮らしの外出支援に効果的です。
■ 家族目線でのポイント
・定期的に「外出の予定」を一緒に立てる
・交通手段が途絶えた時の“代替プラン”を話し合っておく
・緊急時のために、地域交通・タクシー会社の電話番号を紙にまとめておく
これらを日常の会話に取り入れるだけでも、
「親を守る安心感」は大きく変わります。

■ まとめ
地方で暮らす高齢者にとって、「移動の自由」は生活そのものです。
バスが減っても、地域交通・家族・テクノロジーの力で支え合えば、
外出をあきらめる必要はありません。
一人にしない、一緒に考える。
それが、これからの“移動弱者時代”に求められる家族の形です。
🚗 安全・快適な移動の味方「電動シニアカー」という選択
バスや電車の便が減って、買い物や病院に行くのもひと苦労。
そんな悩みを抱える高齢者の方が、全国的に増えています。
「免許は返納したけれど、まだ自分の力で出かけたい」
「家族に迷惑をかけずに買い物や通院をしたい」
―― そんな声に応えるのが、今注目されている 電動シニアカー です。
電動シニアカーは、歩道を走れる「歩行者扱い」の乗り物で、
時速6km前後と安全な速度設計。
運転免許も不要で、誰でも気軽に利用できます。
また、最近のモデルはバッテリーの持ちが良く、
坂道や段差にも強いタイプも登場しています。
屋根付きや折りたたみ式、軽量タイプなど、
使う方の生活スタイルに合わせた選び方が可能です。
🏡 家族にとっても安心の選択肢
一人暮らしの親御さんが「買い物難民」にならないように。
遠く離れていても、安全な移動手段をプレゼントする という形で、
家族からの支援にも向いています。
「もし転んだら…」「車に乗せてあげたいけど忙しい…」
そんな日常の不安を、少しでも減らせるのが電動シニアカーです。
👉 今すぐチェック!
人気の電動シニアカーは、試乗サービスや補助金制度もあります。
「高齢者の移動問題」を解決する、第一歩として検討してみませんか?
👇【おすすめ】安全・快適な電動シニアカー特集はこちら👇
🌱 応援クリックで元気と癒しをお届け中 🌱
↓気に入ったら、気軽にポチッとお願いします!↓
●、【遠く離れた親を見守る安心の方法:家族の不安を減らす5つの工夫】



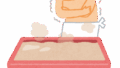
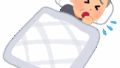
コメント