先日に高齢者の睡眠について1記事作りましたが、私も高齢に差しかかって年齢を重ねると、「夜なかなか眠れない」「眠ってもすぐに目が覚める」「ぐっすり眠った感じがしない」といった悩みを抱える方が増えて目覚めが非常に良くなかったものです。 これは加齢に伴い、体内時計のリズムが変化することや、深い眠り(ノンレム睡眠)が減少することが一因とされています。さらに、日中の活動量の低下や持病による不快感、薬の副作用も影響します。
よくある困りごと、パターン
- 夜中に何度も目が覚める
- 早朝に目が覚めて二度寝できない
- 眠っても疲れが取れない
- 昼間に強い眠気がある
- 睡眠不足から気分が落ち込みやすい
睡眠障害がもたらす影響
睡眠の質が低下すると、心身の健康に大きな影響を及ぼします。
- 記憶力や集中力の低下 → 認知症リスクの増加
- 免疫力の低下 → 病気にかかりやすくなる
- 転倒や骨折のリスク上昇 → 夜間トイレでの不安
- 気分の落ち込みや不安感 → うつ症状へつながる可能性
睡眠は「健康寿命」を左右する重要な要素です。
解決策と工夫
- 生活リズムを整える
- 毎朝同じ時間に起き、日光を浴びる
- 昼寝は20分以内にとどめる
- 日中の活動量を増やす
- 軽い運動や散歩を取り入れる
- 趣味や人との交流で心身を活性化
- 寝室環境を整える
- 静かで暗く、涼しい環境をつくる
- 寝具を体に合ったものにする
- 寝る前の習慣を工夫する
- スマホやテレビを控え、読書や音楽でリラックス
- 温かいお風呂で体温を上げる
- 医師への相談
- 不眠が長引く場合は、睡眠薬に頼る前に専門医に相談
- 服薬中の薬が睡眠に影響していないか確認
高齢者の睡眠の質を高めるには、毎朝決まった時間に起きて日光を浴び、昼寝は短時間にとどめることが大切です。 日中の散歩や軽い運動で体を動かし、夜は静かで快適な寝室環境を整えましょう。就寝前はテレビやスマホを控え、音楽や読書で心を落ち着けると効果的です。眠れない日が続く場合は、薬に頼る前に医師へ相談することが安心につながります。
家族の視点から
高齢の親が「寝れない」「夜中に何度も起きる」と訴えると、家族としても心配になります。
- 親が十分に眠れていないことで日中に転倒しないか
- 睡眠不足から気分が落ち込み、孤独感を深めていないか
- 認知症や生活習慣病のリスクが高まっていないか
家族ができることは、
- 生活リズムを一緒に整える(朝の散歩や食事の時間をそろえる)
- 寝室環境の見直しをサポートする
- 本人の「眠れない」という不安を受け止め、否定せずに寄り添う
- 必要に応じて医療機関をすすめる
親の睡眠を守ることは、結果的に家族の安心にもつながります。
まとめ
高齢者にとって「眠りの質」は、健康と生活の質を大きく左右します。
眠れないことは「仕方ない老化現象」ではなく、生活習慣や工夫、家族のサポートで改善できる場合が多いものです。
家族にとっては「親の眠りを見守ること」が、心身の健康を保ち、長く元気に暮らすための大切なケアの一つとなります。
又、次回は睡眠に質を大きく関与するメラトニンという「睡眠ホルモン」についての内容を次回の記事で紹介しますので是非、参考にしてくださいね!
🌱 応援クリックで元気と癒しをお届け中 🌱
↓気に入ったら、気軽にポチッとお願いします!↓
●、【高齢者の睡眠の質が低下する理由とは? 眠れない夜を改善するための工夫と対策】


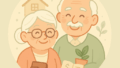
コメント